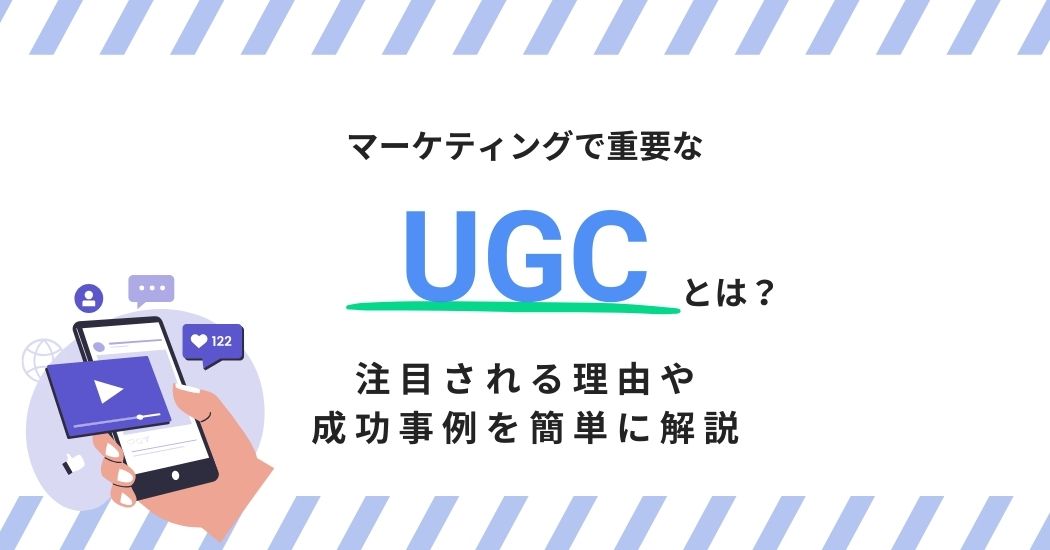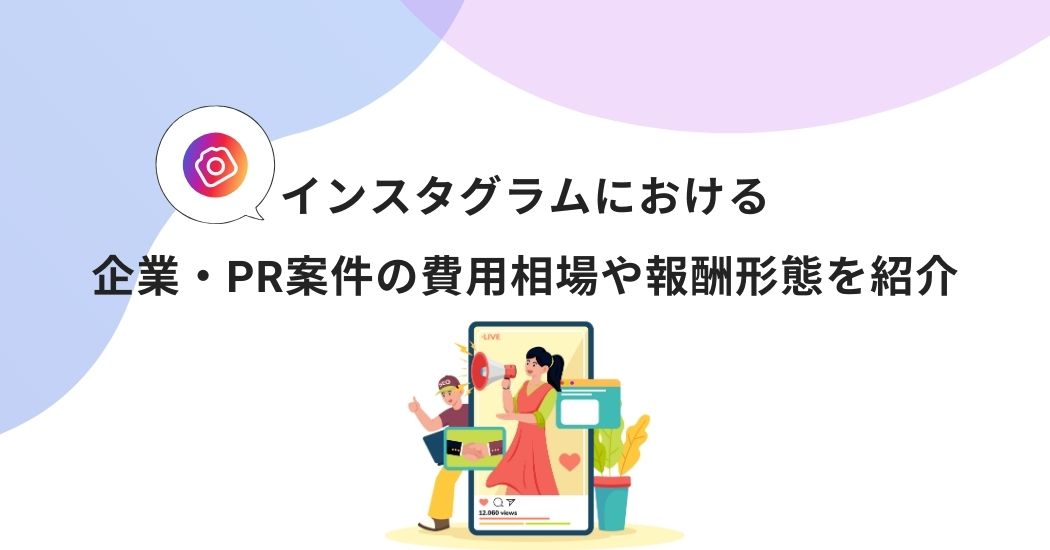「SNSマーケティングは顧客に不信感を与える?」
「インフルエンサーってどう選べばいいの?」
という疑問をお持ちではありませんか?
本記事では、そんな疑問の解決に役立つ内容を
- SNSマーケティングが「怪しい」と思われる理由
- インフルエンサーを活用したSNSマーケティングの注意点
- インフルエンサーの選び方
の順に解説します。
SNS・インフルエンサーマーケティングの導入に興味をお持ちの方に役立つ記事です。
ぜひ最後までご覧ください。
SNSマーケティングが「怪しい」と思われるのはなぜ?

まずは、なぜSNSマーケティングが「怪しい」と言われることがあるのかについて、解説していきます。
誇張表現や誤解を招くことがある
SNSでは、過激な表現を使った方が投稿が拡散されやすくなり、ユーザーの目に触れる機会も多くなります。
「このサプリメントを飲むだけで-10kg!」などのキャッチコピーはその一例であり、やり過ぎると優良誤認につながる可能性があります。
これでは、消費者の期待を必要以上に高めてしまうため、実際の使用感と差異が生じてしまい信頼を損ないかねません。
ステルスマーケティングと勘違いされることがある
ステルスマーケティングとは、宣伝や広告であることを消費者に気付かれないように行うマーケティング活動のことを指し、「ステマ」と呼ばれることもあります。
以前は、インフルエンサーマーケティングでも、プロモーションであることを伏せての投稿などが多く行われていました。
ステルスマーケティングは消費者が自主的・合理的に商品を選択する妨げになるため、令和5年10月から景品表示法違反として規制されています。
そのため、消費者にステルスマーケティングを行うと、ブランドの信用は大きく損なわれます。
インフルエンサーを活用して広告を行うのであれば、しっかりとユーザーが認知できるように記載を行い、適切にインフルエンサーマーケティングを行っていくことで、最終的なユーザーの信頼を獲得することにもつながります。
透明性に欠ける印象を与えることがある
インフルエンサーの投稿では、企業のホームページへの導線が確保されていなかったり、商品の詳細を知ることができなかったりする場合があります。
企業の方針や商品の成分・効果などが不明瞭だと、消費者に悪い印象を与えかねません。
適切に商品説明のページリンクを貼るなど、透明性を意識するのがポイントです。
インフルエンサーの投稿内容をコントロールしづらい
インフルエンサーマーケティングは、プロモーションしてほしい商品や大まかな宣伝内容などを事前に擦り合わせますが、細部はインフルエンサーに一任することが多いです。
インフルエンサー自身が考えて作成する部分も多く、投稿内容をコントロールしづらいことがあります。
また、プロモーションとは無関係な他の投稿でインフルエンサーが炎上するリスクもあります。
そうした場合、ユーザーに「炎上したインフルエンサーが紹介している商品」というマイナスイメージを与えかねません。
インフルエンサーを活用したSNSマーケティングで注意すべきこと

ステルスマーケティングを避ける
先ほど紹介したように、ステルスマーケティングは消費者からの信頼を損なうことにつながります。
「広告」「プロモーション」などの表示を忘れないよう注意し、ステルスマーケティングを避けることを徹底しましょう。
また、炎上を防ぐために、景品表示法や薬機法にも違反しないよう注意が必要です。
投稿内容についてインフルエンサーと相談しておく
ブランドの意図や目的をインフルエンサーと共有し、フォロワーにどんなメッセージを伝えてほしいのかを理解してもらうのがよいでしょう。
投稿のトンマナや付けてほしいハッシュタグなど、詳細なルール作成も重要です。
完成後に理想のプロモーションとのギャップが生まれないようにするため、依頼前に理想像を固めておくのがおすすめです。
インフルエンサーの個性を活かす
炎上を避けよう、プロモーションの目的を達成しようと考えていると、インフルエンサーに守ってもらう規約が多くなりがちです。
しかし、インフルエンサーは、その個性あふれる投稿内容によって人気を博しています。
そのため、規約が多くなりすぎて個性が失われればフォロワーの印象にも残りづらくなり、結果的に広告効果が減少してしまいます。
フォロワーの興味や関心を熟知しているインフルエンサーの意見を取り入れながら、個性を活かした投稿を作成してもらうのがよいでしょう。
インフルエンサーマーケティングに必要不可欠な「KPI」と「KGI」

達成状況の評価指標となる「KPI」
KPIとは、Key Performance Indicator(重要業績評価指標)の略です。
目標を達成するための進捗を測る指標であり、達成状況を細かく把握するために設定します。
KPIに沿って効果検証を行うことで、成功・失敗それぞれの原因を分析し、今後に活かすことができます。
KPIは複数個設定することが多く、具体的に数値化していることや、達成可能な範囲であること、継続的に測定できることなどを意識して設定すると判断しやすくなります。
最終目的である「KGI」
KGIとは、Key Goal Indicator(重要目標達成指標)の略です。
マーケティングなどの最終的な目的のことを指し、達成したかどうかを分かりやすくするために数値を用いて設定するのが一般的です。
- ホームページの訪問者数を2倍にする
- 10代からの購入数を10%増加させる
などの目標がこれにあたります。
こうした目標や指標を設定しておくことで、インフルエンサーマーケティングが終了した時に、費用対効果や施策を継続すべきかなどについて考えやすくなります。
インフルエンサーの選び方

フォロワー数・閲覧数
インフルエンサーを選ぶうえで指標の一つとなるのが、フォロワー数・投稿の閲覧数です。
単に認知度の向上を目的とするのなら、規模の大きいインフルエンサーに依頼するのがおすすめです。
しかし、規模の大きいインフルエンサーを起用すれば効果が大きいとも言い切れないため、フォロワー数・閲覧数だけを注視するのはおすすめできません。
エンゲージメント率
フォロワーが多かったとしても、過去に獲得したフォロワーがほとんどである場合など、アクティブでないフォロワーが多ければ広告効果は低くなります。
そこで、フォロワーがどれだけ投稿にアクションを起こしているかを示すエンゲージメント率を確認するのがおすすめです。
いいねやコメントなど、投稿への反応数でエンゲージメント率を測ることができます。
どのような投稿でエンゲージメント率が高くなっているかも把握しながら、インフルエンサーの特徴を把握しましょう。
ターゲット層
インフルエンサーのフォロワー層と商品のターゲット層が一致しているかというのは、インフルエンサーを選ぶうえで重要な視点です。
インフルエンサーのジャンルだけでフォロワー層を判断するのではなく、男女比や年代比にも注目するのがおすすめです。
ファッションジャンルで活躍する女性インフルエンサーでも、男性のフォロワーを多く抱えている場合などがあります。
PR投稿の経験
PR投稿の経験は必須ではありませんが、経験があった方がスムーズにプロジェクトを進められます。
過去のPR投稿をチェックすれば、PR内容の充実度や丁寧さを知ることができます。
中には案件を断っているインフルエンサーもいるため、PRの依頼ができるかどうかも確認できます。
インフルエンサーに依頼する方法

直接インフルエンサーに依頼する
SNSなどで宣伝したい商品とマッチしたインフルエンサーを見つけることができれば、直接連絡して依頼をするのがよいでしょう。
中間マージンが発生しないため、依頼料のみで費用を抑えて契約できます。
一方で、インフルエンサーの数が多く、選ぶのが難しいというデメリットがあります。
インフルエンサーのキャスティング業者に依頼する
インフルエンサーのキャスティング業者を利用するのも有効な手段です。
投稿してほしいプラットフォーム、宣伝したい商品やブランドの雰囲気などから、最適なインフルエンサーを選んでくれます。
企画立案から実施までワンストップでの支援や、AIによるデータ分析を行っている業者もあります。
SNSを見て回るよりも効率的に、インフルエンサーマーケティングの効果を最大化することができるでしょう。
まとめ

今回は、SNSマーケティングが「怪しい」と思われる理由や、そう思われないための注意点について解説しました。
SNSマーケティングは誤った手法を用いてしまうと顧客に不信感を与えることもありますが、正しく行えば大きな効果を得られます。
Kolr(カラー)は、世界最大級のインフルエンサーマーケティングプラットフォームです。
競合他社の投稿やインフルエンサータイアップ状況がわかるため、市場の動向を見ながらインフルエンサーマーケティングの導入を判断することができます。
興味をお持ちの方は、ぜひ登録し、無料トライアルでニーズに最適なインフルエンサーを検索してみてください。